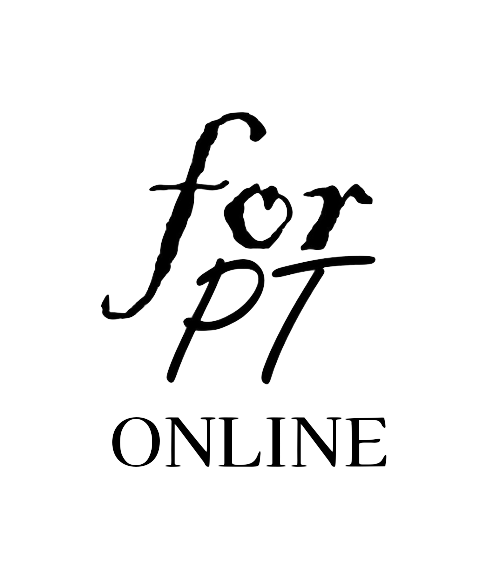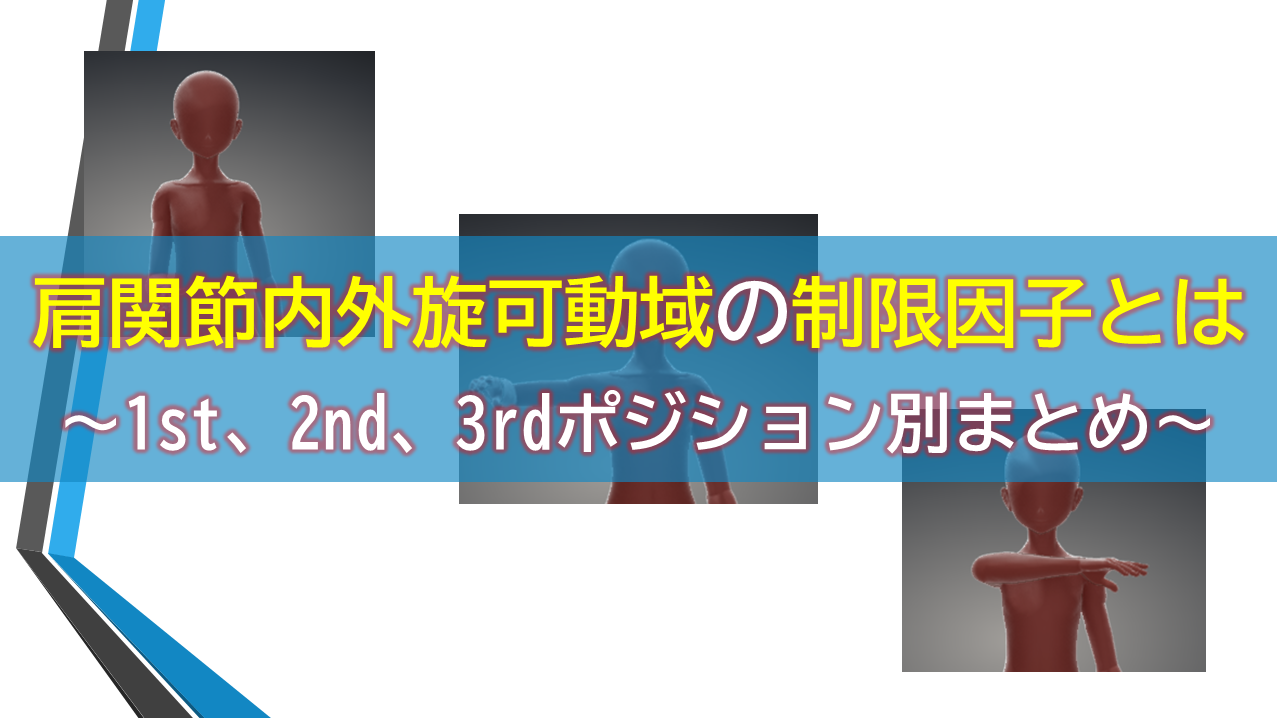
🔻新・臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻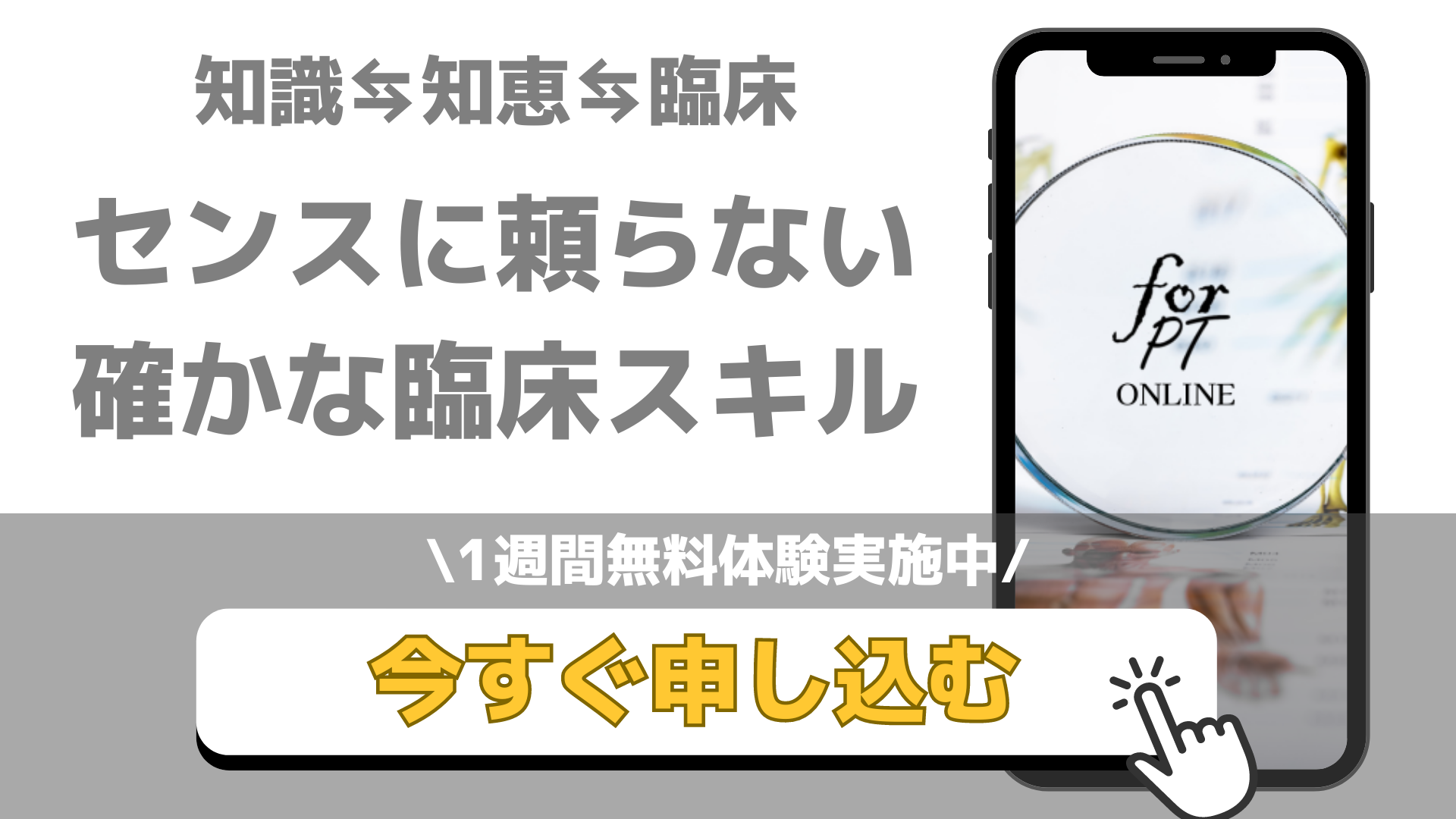
肩甲上腕関節(以降肩関節)の制限因子を一度整理しませんか?
五十肩や上腕骨骨折後などに、いわゆる拘縮肩を抱える患者さんはとても多いです。
肩関節可動域の獲得は、理学療法士が専門性を持ってアプローチしなければならない大事な対象のひとつです。
今回は、その基礎となる肩関節のポジション別の可動域制限因子をまとめたいと思います。
まず、肩関節肢位は便宜上、3つのポジションに分けられています。
| ・1stポジション ・2ndポジション ・3rdポジション |
1stポジション
肘関節90°、上腕下垂位で肩関節屈曲、外転ともに0°の肢位です。
ここでの回旋運動は水平面上の運動を表します。

1stポジション
2ndポジション
肘関節90°、肩関節屈曲0°、外転90°の肢位です。
ここでの回旋運動は矢状面上の運動を表します。
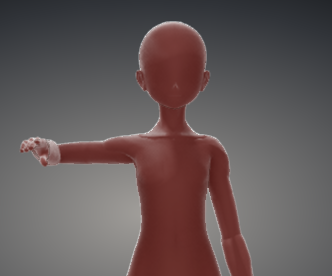
2ndポジション
3rdポジション
肘関節90°、肩関節屈曲90°、外転0°の肢位です。
ここでの回旋運動は前額面上の運動を表します。
 3rdポジション
3rdポジション
そして、各ポジションの肩関節内外旋を制限する軟部組織がこれらです。
|
1stポジション 【内旋】 【外旋】 |
|
2ndポジション 【内旋】 【外旋】 |
|
3rdポジション 【内旋】 【外旋】 |
臨床では、棘下筋や小円筋および後方関節包などの後方支持組織のタイトネス、烏口上腕靭帯のタイトネス、三角筋のスパズムや滑走不全が、非常に多くみられます。
ここで大事なポイント!!
3つのポジションはあくまで便宜上、決められているだけ!! です。
大切なのは、
3つそれぞれのポジションに肩関節が近づくにつれて、上記で挙げた組織たちが制限する割合が高まる ということです。
例を挙げると、、、
「肩関節2ndポジションでは他動で90°外旋するけど、その外旋位を保持したまま、1stポジションまで持っていくと段々抵抗感が強くなり外旋可動域も減ってくるぞ」といったセラピストの感覚が大事です。
この場合は、腱板疎部や烏口上腕靭帯に制限があるのかな?などと抵抗感のベクトルを意識することで、制限組織をより早く的確にみつけていけるようになります。
ただ教科書的に覚えるのではなく、実際に抵抗感を確かめながら評価を進めると、臨床スキルが高まると思います。
情報は随時更新していきます。
🔻新・臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻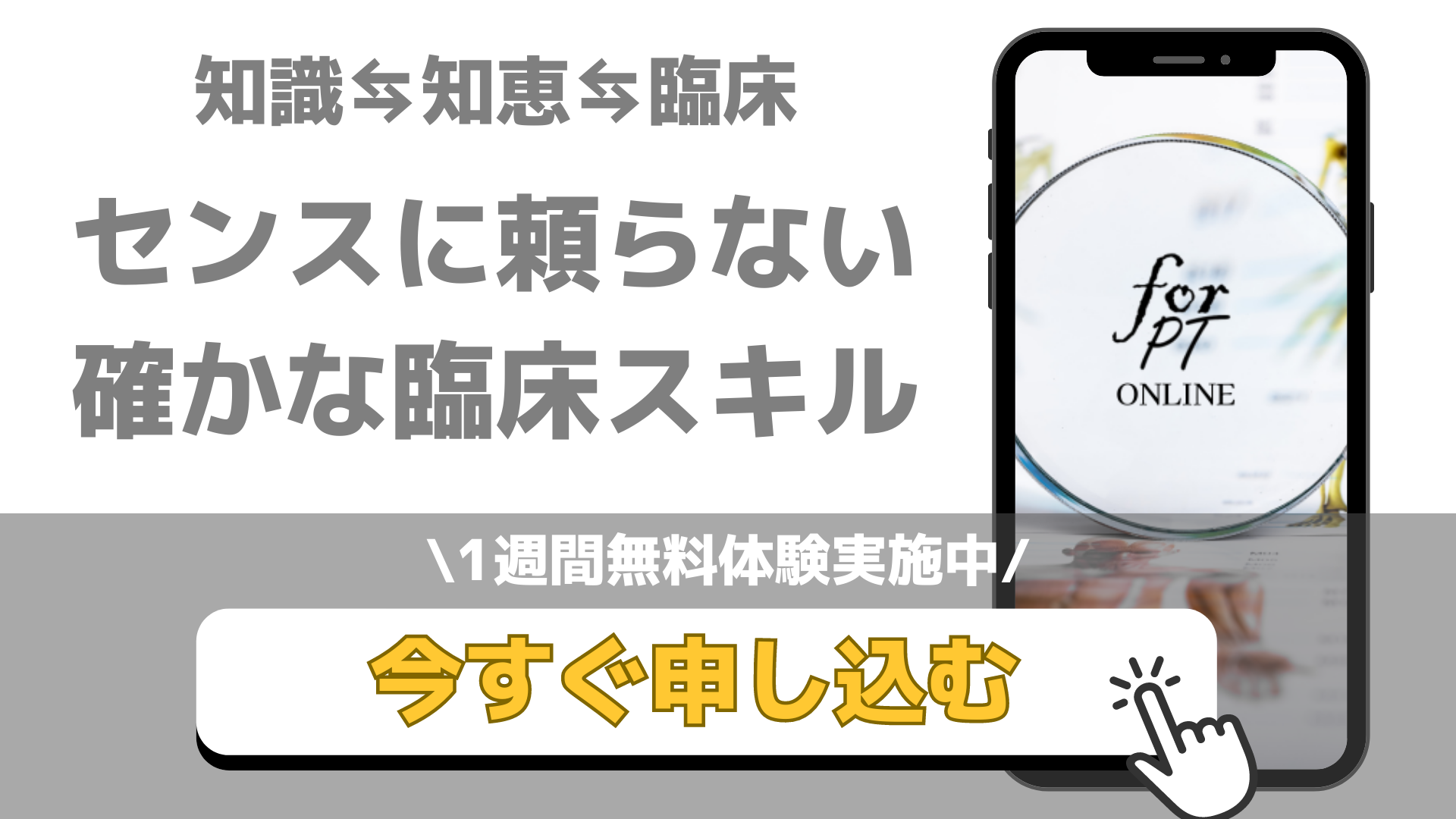
参考・引用文献
1)林典雄:肩関節拘縮の評価と運動療法.株式会社運動と医学の出版社,2013.
2)Neumann, Donald A.:筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版. 医歯薬出版株式会社, 2018.
3)工藤慎太郎:運動器障害の「なぜ?」がわかる評価戦略.株式会社医学書院,2018.